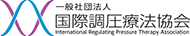ホーム >
低圧低酸素環境における危険性の見解
一般財団法人 国際調圧療法協会
理事 船渡和男
低圧低酸素環境トレーニング(高地トレーニング)において「標高が高ければ(より低酸素、より低圧なら)それなりの効果がある」スポーツに関係するコーチや選手を含め一般的にも強い思い込みがあると感じます。
高地トレーニングで成功した選手のトレーニングばかりが多くのメディアで取り上げられますが、その裏で環境に適応できず却ってコンディショニング不良(オーバートレーニング)になってしまったケースは数多くあること、そして大切なことは低酸素・低圧トレーニングには個人差は非常に大きいということ、この点を考慮しておかなければならないと思います。
現在この個人差をもたらす要因について研究が進んでいますが、まだはっきりとした
エビデンスは得られていない状況です。
ですから、高地トレーニングでは、2000m以下のいわゆる準高地での高地順化や生体反応から順次進めていくのが、現段階ではリコメンドされているところです。
また””Live high, Train low””といって、高地で滞在(食事、睡眠、休息など)しながらのトレーニングは準高地または平地で行うことによって、有効なパフォーマンスの改善が得られるという手法も提案されています。もちろんそれらの前には、メディカルチェックにより特に呼吸心臓循環系の異常所見がないことを前提としています。
当協会が研究している、低圧低酸素環境(標高1000~1500m)と常圧常酸素環境を交互に繰り返す「調圧」という方法は論理的見解からみても、問題が起こることはないと考えます。
問題はユーザー側の間違った気圧法の使途によって危険を招いていることです。
我々も含めた研究者により解明していくことが必要であると考えます。
船渡和男 Ph.D.
国士館大学大学院スポーツ・システム研究科 特任教授
東京体育学会 会長